破風、鼻隠しからの雨漏り、軒天への雨漏り、それぞれの発生原因と補修方法


ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00
0120-991-887

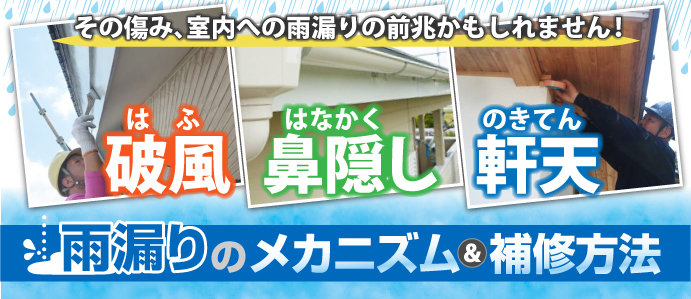


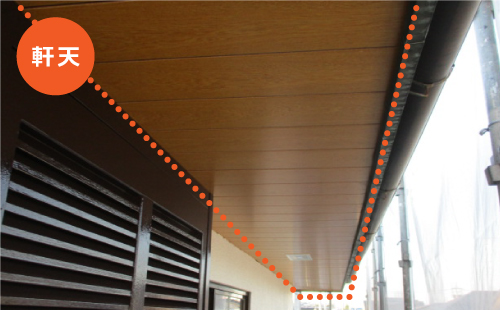

 色褪せ
色褪せ 
 シーリングの傷み
シーリングの傷み 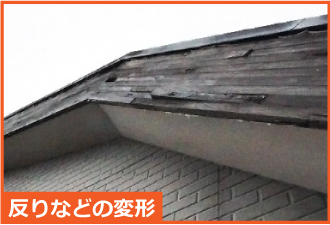
 反りなどの変形
反りなどの変形 
 腐食
腐食  軒天の劣化と腐食
軒天の劣化と腐食 

 室内への雨漏り
室内への雨漏り 

 色褪せ
色褪せ 
 シーリングの傷み
シーリングの傷み 
 屋根の不具合
屋根の不具合  雨樋の不具合との排水不良
雨樋の不具合との排水不良 

 腐食
腐食 
 軒天の劣化と腐食
軒天の劣化と腐食 
 室内への雨漏り
室内への雨漏り 
 屋根からの雨漏り
屋根からの雨漏り 
 雨樋の排水不良による雨漏り
雨樋の排水不良による雨漏り 
 バルコニーやベランダの床面の裏の軒天雨漏り
バルコニーやベランダの床面の裏の軒天雨漏り 
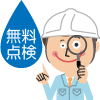
 切妻屋根の妻側(横から見て三角部分)が破風です
切妻屋根の妻側(横から見て三角部分)が破風です  雨樋を取り付ける場所が鼻隠しです
雨樋を取り付ける場所が鼻隠しです  屋根の裏面の天井に当たる部分が軒天です
屋根の裏面の天井に当たる部分が軒天です  破風は雨と風が当たりやすく、傷みやすい部分なので雨漏りの原因となりやすいです
破風は雨と風が当たりやすく、傷みやすい部分なので雨漏りの原因となりやすいです  破風からの雨漏りが室内へ浸入してくるまでには段階があります
破風からの雨漏りが室内へ浸入してくるまでには段階があります  鼻隠しは取り付けられた雨樋や屋根の不具合から傷みます
鼻隠しは取り付けられた雨樋や屋根の不具合から傷みます  軒天へ雨漏りする原因にはさまざまなものがあります
軒天へ雨漏りする原因にはさまざまなものがあります  建物の構造によっては破風や軒天付近の雨漏りが室内へ漏水しにくいケースもあります
建物の構造によっては破風や軒天付近の雨漏りが室内へ漏水しにくいケースもあります  軒天の剥がれを放置すると鳥獣の巣にされる可能性が高まります
軒天の剥がれを放置すると鳥獣の巣にされる可能性が高まります  破風や軒天に違和感や変化を感じたら信頼できる屋根業者に点検してもらいましょう
破風や軒天に違和感や変化を感じたら信頼できる屋根業者に点検してもらいましょう
















