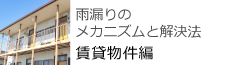雨漏り解決の秘訣!プロが手掛ける入母屋屋根の修理現場

「雨が強く降ると室内に雨漏りがする…」そんなお悩みを抱えていませんか?
雨漏りは、放置すると建物の構造を傷つけ、カビの発生など健康被害にもつながりかねない深刻な問題です。
早期に原因を特定し、適切な処置を施すことが、お客様に安心して暮らしていただける住まいを守るために何よりも大切です。
先日、名古屋市熱田区にお住まいのお客様からこのようなご相談を受け、雨漏り診断と工事のご提案をさせていただきました。
そしてこの度、正式にご依頼をいただき、いよいよ雨漏り修理工事に着手することになりましたので、その詳細を現場ブログとしてご紹介します。
弊社、直通ダイヤルは、こちらになります↓↓↓


雨漏りの原因となっていた隅棟(すみむね)部分の修理は、まずその解体作業から始まります。
私たちは、熟練の技術で棟瓦(むねがわら)を一つひとつ丁寧に解体し、慎重に取り外していきます。
今回の修理では、既存の棟瓦を再利用するため、作業中は瓦を破損させないよう細心の注意を払うことが非常に重要です。
取り外した際に出てくる古い屋根土は、もう使うことができません。
これらはすべて土嚢(どのう)袋に詰めて適切に処分します。
この解体作業は、単に瓦を取り外すだけではありません。
雨漏りの痕跡を詳しく確認し、長年の雨風にさらされてできた劣化や、過去の施工不良など、隠れた損傷がないかを見極める大切な工程なんです。
私たちが普段目にすることのない屋根の内部には、雨漏りの根本原因が潜んでいることがあります。
私たちは、そうした見えない部分もしっかりと診断し、根本的な解決を目指します。
プロの目が光ることで、単なる表面的な修理ではなく、本当の意味での雨漏り解決へとつながるのです。
解体作業が完了したら、いよいよ新しい土台作りに入ります。
隅棟の土台となる熨斗瓦(のしがわら)を取り付けるために欠かせないのが、接着剤代わりになる屋根土(やねつち)です。
この屋根土を隅棟の芯に丁寧に置いていきます。
屋根土とは、赤土・砂・粘土・藁すさ・水などを混ぜ合わせ、時間をかけて発酵させた、屋根工事専用の土のことです。
発酵させることで生まれる独特の粘り気が、陶器製の屋根瓦をしっかりと接着してくれるんです。
屋根土を隅棟の芯に置いたら、土台の熨斗瓦を取り付ける前に、その表面に屋根漆喰(しっくい)を隅棟部全体に塗っていきます。
この漆喰が、雨水が侵入するのを防ぐ大切な防水層となるんです。
瓦をただ並べているだけでは、雨漏りを完全に防ぐことはできません。
こうした見えない部分の丁寧な下地処理こそが、雨漏りを防ぎ、屋根を長持ちさせる秘訣なのです。
職人の細やかな手作業によって、雨水の侵入を許さない強固な土台が築かれていきます。
入母屋(いりもや)屋根の修理では、雨漏りを防ぐための大切な工夫があります。
それは、加工した瓦を隅棟(すみむね)の下方に、まるで隠すように先に配置することです。
なぜこのような一手間を加えるのでしょうか?
実は、この加工瓦を置く場所は、雨水が流れる重要な通路になります。
もし何も考えずに隅棟瓦を施工してしまうと、その瓦が水の流れを堰き止めてしまい、結果として雨水が滞留し、雨漏りの原因となってしまうのです。
これこそが、入母屋屋根で雨漏りが発生しやすい理由の一つに挙げられます。
先に加工した瓦を置いておくことで、隅棟部の下部に雨水がスムーズに流れるための「トンネル」が作られます。
このトンネルを雨水が通ることで、隅棟内部への水の侵入を防ぎ、大切な住まいを雨漏りから守るのです。
続いて、隅棟の土台となる一段目の熨斗瓦(のしがわら)を取り付けていきます。
この最初の瓦が、全体の安定性を左右する重要な役割を担います。
隅棟全体が地震や強風で崩れ落ちないよう、最終的には針金でしっかりと縛り固定します。
この針金が通るように、土台の熨斗瓦を置く際に、あらかじめ針金の土台部分も一緒に設置しておきます。
そして、二段目以降の熨斗瓦でこの針金を挟み込むように、順序良く瓦を上段へと積み上げていくのです。
これにより、瓦同士が一体となり、強固な棟が完成します。
こうした見えない部分への細やかな配慮と地道な作業こそが、何十年も風雨に耐えうる長持ちする屋根を作り上げる秘訣です。
積み重ねてきた熨斗瓦(のしがわら)が、いよいよ隅棟の最終段階へ。
一番上には、屋根の顔ともいえる冠棟瓦(かんむりむねがわら)を被せていきます。
この冠棟瓦を設置したら、いよいよ最終工程です。
積み上げた隅棟全体が地震や強風で崩れないよう、事前に仕込んでおいた針金でしっかりと固定していきます。
この作業で、隅棟は一体となり、堅牢な構造として完成します。
最後に、棟終い(むねじまい)と呼ばれる棟の端部に屋根漆喰(しっくい)を塗っていきます。
これは、積み上げた熨斗瓦の隙間から雨水が侵入するのを防ぐ、大切な防水処理です。
また、鬼瓦(おにがわら)の背中側と隅棟瓦が接する部分には、施工上わずかな隙間ができてしまうことがあります。
この隙間も雨水の侵入口となるため、ここにも屋根漆喰を塗ってしっかりと防水処理を施します。
この部分は、屋根工事の職人さんや左官屋さんから「鬼周り漆喰(おにまわりしっくい)」とも呼ばれる、雨漏りを防ぐための非常に重要なポイントです。
こうして屋根漆喰で隅々まで防水処理を行うことで、今回の隅棟部の積み直し修理はすべて完了しました。
見た目の美しさだけでなく、見えない部分への徹底したこだわりこそが、雨漏りから家を守る大切なポイントです。
私たちはお客様の大切な住まいを長く守るため、一切の妥協なく作業を進めています。

今回の記事では、名古屋市熱田区のお客様宅での雨漏り修理、特に
入母屋屋根の隅棟積み直し工事の全工程をご紹介しました。
雨漏り修理は、単に表面を直すだけでなく、原因となる部分を正確に特定し、適切な材料と高い技術力で根本から解決することが重要です。
古い瓦の丁寧な解体から始まり、屋根土や漆喰を使った土台作り、入母屋屋根ならではの雨水経路確保の工夫、そして最終的な防水処理まで、一つひとつの工程がお客様の住まいの安心を支えています。
- 雨漏り修理は解体から始まる:原因箇所の隅棟を慎重に解体し、隠れた損傷を見極めることが重要です。
- 見えない部分の丁寧な作業が鍵:屋根土や漆喰による強固な土台作りと防水処理が、雨漏りを防ぐ要となります。
- 入母屋屋根には特有の工夫が必要:加工瓦で雨水経路を確保するなど、構造を理解した専門的な施工が不可欠です。
- 職人の技術とこだわりが安心を創る:最終的な針金での固定や隅々までの漆喰処理など、見えない部分への徹底した配慮が長期的な安心を支えます。

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は
下記までお気軽にお問い合わせください!
受付時間 9時~17時(平日)
※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。
0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com
※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。
トップページに戻る⇒
こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】
地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。
お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。
初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。
雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください
1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談
2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談
3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談
4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談
5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談
6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談
7.照明器具など電気工事などのご相談
8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談
9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談
アメピタ名古屋南店TOPはこちら
アメピタ名古屋南店
TOPはこちら