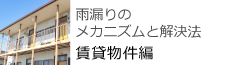小平市学園東町で外壁からの雨漏りにお困りとの連絡をいただきこの度調査を行うこととなりました。
外壁からの雨漏りは、建物の外装に関する重要な問題です。主な原因としては、外壁の目地の劣化、サッシ枠の劣化、外壁材の反りや変形、外壁材を止める釘の劣化、そして水切り金具の劣化が挙げられます。
外壁の目地の劣化は、シーリング材の経年劣化によって起こります。シーリング材が痩せたり、ひび割れたり、剥がれたりすることで、目地に隙間が生じ、そこから雨水が浸入します。シーリング材の寿命は通常5〜10年程度です。
サッシ枠の劣化も雨漏りの原因となります。サッシ枠と外壁材の隙間を埋めるシーリング材が劣化したり、サッシ枠の縦横のパッキンが劣化したりすると、雨水が浸入する可能性が高くなります。
外壁材自体の問題も雨漏りを引き起こす可能性があります。モルタル外壁のヒビ割れや窯業系サイディングの反り、変形、割れなどが隙間を作り出し、雨水の侵入経路となることがあります。
外壁材を固定する釘の劣化も見逃せません。釘が錆びたり浮いたりすると、雨水が下地に浸入しやすくなります。さらに、錆びた釘が膨張して外壁材にヒビ割れを引き起こすこともあります。
水切り金具の劣化も雨漏りの原因となります。異なる部材が接合する箇所(取り合い)に使用される水切り金具が劣化したり、そのつなぎ目のシーリング材が劣化したりすると、そこから雨水が浸入する可能性があります。
外壁塗装は美観の向上が主な目的であり、雨漏りの解決策とはなりません。雨漏りが発生した場合は、原因を特定し、適切な修理を行うことが重要です。専門業者による調査と修理が必要な場合もあるため、早めの対応が求められます。
 外壁目地の雨漏りをグルーガンで補修することは推奨されません。グルーガンは一時的な応急処置として使用できる可能性はありますが、長期的な解決策としては適していません。
外壁目地の雨漏りをグルーガンで補修することは推奨されません。グルーガンは一時的な応急処置として使用できる可能性はありますが、長期的な解決策としては適していません。 外壁目地の雨漏り補修には、専用のコーキング材(シーリング材)を使用するのが適切です。コーキング材は外壁の動きに対応できる伸縮性があり、耐候性や耐久性に優れています。
正しい補修方法としては、まず既存のコーキングを完全に除去し、目地を清掃します。次に、目地の両脇にマスキングテープを貼って養生し、プライマーを塗布します。その後、コーキングガンを使用して新しいコーキング材を充填し、ヘラで成形します。
この作業は「打ち替え工法」と呼ばれ、コーキングの防水性や気密性を回復させる効果があります。一方、グルーガンで補修した場合、外壁の動きに対応できず、すぐに剥がれたり割れたりする可能性が高くなります。
また、外壁目地の補修は専門的な知識と技術が必要な作業です。DIYでの補修は基本的に推奨されず、特にグルーガンのような不適切な材料を使用することは避けるべきです。
雨漏りは建物に深刻な損傷を与える可能性があるため、専門業者による適切な補修を行うことが重要です。 したがって、外壁目地の雨漏り補修にグルーガンを使用することは避け、専門業者に相談して適切な材料と方法で補修を行うことをお勧めします。

サッシの上部からの雨漏りは、建物の外装に関する重要な問題です。
この現象は、サッシ自体に原因があることは稀で、多くの場合はサッシより上部の構造に問題があります。 主な原因としては、外壁の目地にあるコーキング材(シーリング材)の劣化が挙げられます。コーキング材は経年劣化により、ひび割れや剥がれが生じ、そこから雨水が浸入する可能性があります。特に上階のサッシ周りや外壁の目地のコーキング材が劣化すると、外壁内に雨水が浸入しやすくなります。
また、外壁のヒビ割れも雨漏りの原因となります。サッシ付近の外壁に小さなヒビが入ると、そこから長時間かけて雨水が浸み込むことがあります。さらに、サッシから離れた上部の外壁にヒビがある場合、そこから浸入した雨水が下に伝わってサッシ上部で雨漏りとなって現れることもあります。
施工不良も重要な要因です。特に、サッシ上部のフィンと防水シートの施工が適切でない場合、そこから室内側へ雨水が侵入し、雨漏りが発生します。
さらに、サッシ上部の屋根に問題がある場合も雨漏りの原因となります。屋根の破損部分から浸水した雨水が壁の内部を伝い、サッシ部分で雨漏りとして現れることがあります。
これらの問題に対処するには、専門的な知識と技術が必要です。DIYでの修理は困難であり、専門業者による適切な診断と修理が推奨されます。修理方法や費用は問題の原因や範囲によって大きく異なるため、複数の業者から見積もりを取り、適切な対応を選択することが重要です。

霧除け(庇)のビス止め箇所からの雨漏りは、建物の外装における一般的な問題です。この現象は主に、ビスを通して雨水が浸入することで発生します。
霧除けは建物の外壁から突き出した構造物であり、雨風や紫外線の影響を直接受けやすい位置にあります。
そのため、経年劣化によってビス周りのシーリング材が劣化したり、ビス自体が緩んだりすることがあります。これらの要因により、ビスの周囲に微細な隙間が生じ、そこから雨水が浸入する可能性が高くなります。
特に注意が必要なのは、霧除けの上部に直接ビスで固定されている場合です。この「脳天打ち」と呼ばれる取り付け方法は、雨水が滞留しやすい場所にビスの穴を作ることになるため、雨漏りのリスクが高くなります。新設時にはシーリング材で防水処理がされていても、時間の経過とともにシーリングが劣化し、雨水の浸入を許してしまうのです。
また、霧除けの材質によっても雨漏りのリスクは変わってきます。木製の場合は腐食、金属製の場合は錆びによる穴あきなどが原因で雨漏りが発生することがあります。
さらに、霧除けと外壁との接合部(取り合い)のコーキングや板金の劣化も、雨漏りの原因となります。 霧除けからの雨漏りを防ぐためには、定期的な点検とメンテナンスが重要です。ビス周りのシーリングの状態を確認し、必要に応じて補修や打ち替えを行うことが効果的です。また、霧除け全体の状態を確認し、材質の劣化や変形がないかチェックすることも大切です。
深刻な雨漏りの場合は、既存の水切り板金を残したまま、新しい板金でカバーする「カバー工法」も有効な対策の一つです。この方法では、見付けを長くした水切り板金を使用することで、より効果的に雨水の浸入を防ぐことができます。
霧除けのビス止め箇所からの雨漏りは、適切な施工と定期的なメンテナンスによって防ぐことができます。しかし、専門的な知識と技術が必要なため、深刻な問題が発生した場合は、専門業者に相談することをお勧めします。
アメピタでは
雨漏り修理33,000円から対応しておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください!
こちらの記事を書いた施工店【アメピタ多摩川支店】
私達「アメピタ多摩川支店」ではお客様に寄り添い、建物にとってもお客様にとっても最適な雨漏り修理のご提案をさせていただきます。
急な雨漏りでどこに電話したらいいのだろう?他社に雨漏り修理をお願いしても雨漏りが止まらなかった。などのお悩みをお持ちの方は是非アメピタの無料相談をご利用ください。雨漏り診断士の有資格者が多数在籍しておりますので、どんな雨漏りも確実に止めることをお約束します!
アメピタ多摩川支店は東京都調布市を所在地とし、お電話を頂いてから最短10分での現地調査や応急処置でご対応させていただいております。
アメピタ多摩川支店TOPはこちら
アメピタ多摩川支店
TOPはこちら