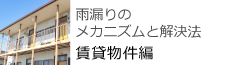雪害によりズレてしまった棟瓦と漆喰の取り直し工事
お客様のお悩みや雨漏り工事のきっかけを伺いました!

今回のご依頼は、築30年の日本瓦が印象的なお家です。
「棟瓦が雪によって崩れてしまい、雨漏りがしているので修理をして欲しい」とお問合わせを頂きました。
インターネットで信頼できる屋根工事専門店を検索されて、弊社のHPをご覧になり「ここなら安心してお願いできる」と連絡をされたそうです。
「棟瓦が雪によって崩れてしまい、雨漏りがしているので修理をして欲しい」とお問合わせを頂きました。
インターネットで信頼できる屋根工事専門店を検索されて、弊社のHPをご覧になり「ここなら安心してお願いできる」と連絡をされたそうです。
屋根全体を見ても、棟部分以外に問題も見られませんでした。この場合、棟瓦のズレのみを直すことも選択肢として考えられますが、漆喰の劣化などの可能性も考えられたので、棟瓦の葺きなおしと漆喰の取り直しをご提案させていただきました。
この状態を放置しておくと、瓦の落下や雨漏り、耐震の危険性も考えられます。実際に雨漏りが発生しておりました。
今回の施工では、次の雨の日が心配で「早急に施工して欲しい!」と施主様が仰られていたので、1日の施工で完了しました。
崩れて曲がってしまっていた棟瓦はしっかりと固定して綺麗に整え、雨漏りの心配や地震の心配なども解消させていただきました。
仕上がりを見た施主様からは「お願いしてよかった!これで安心して過ごせます」と大変喜んで頂けました。ありがとうございました!
屋根の上は普段目に入りませんし、自分では気づきにくい箇所です。雨漏りや屋根のトラブルを防ぐには定期的なメンテナンスが必要です。ご自身がお住まいの屋根が気になる方はお気軽にお問合わせください。
この状態を放置しておくと、瓦の落下や雨漏り、耐震の危険性も考えられます。実際に雨漏りが発生しておりました。
今回の施工では、次の雨の日が心配で「早急に施工して欲しい!」と施主様が仰られていたので、1日の施工で完了しました。
崩れて曲がってしまっていた棟瓦はしっかりと固定して綺麗に整え、雨漏りの心配や地震の心配なども解消させていただきました。
仕上がりを見た施主様からは「お願いしてよかった!これで安心して過ごせます」と大変喜んで頂けました。ありがとうございました!
屋根の上は普段目に入りませんし、自分では気づきにくい箇所です。雨漏りや屋根のトラブルを防ぐには定期的なメンテナンスが必要です。ご自身がお住まいの屋根が気になる方はお気軽にお問合わせください。
工事のきっかけやお問合せまでの不安、アメピタの印象まですべて教えます!!
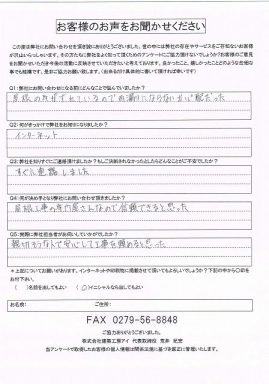
Q1:弊社にお問い合わせになる前にどんなことで悩んでいましたか?
屋根の瓦がずれているので雨漏りにならないか心配だった
Q2:何がきっかけで弊社をお知りになりましたか?
インターネット
Q3:弊社を知りすぐにご連絡頂けましたか?もしご決断されなかったとしたらどんなことがご不安でしたか?
すぐに決断しました
屋根の瓦がずれているので雨漏りにならないか心配だった
Q2:何がきっかけで弊社をお知りになりましたか?
インターネット
Q3:弊社を知りすぐにご連絡頂けましたか?もしご決断されなかったとしたらどんなことがご不安でしたか?
すぐに決断しました
Q4:何が決め手となり弊社にお問い合わせ頂きましたか?
屋根工事の専門屋さんなので信頼できると思った
Q5:実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたか?
親切そうな人で安心して工事を頼めると思った
屋根工事の専門屋さんなので信頼できると思った
Q5:実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたか?
親切そうな人で安心して工事を頼めると思った
棟瓦と漆喰の取り直し工事のビフォーアフター


工事基本情報
施工内容
棟瓦取り直し,漆喰取り直し
施工期間
1日
使用材料
漆喰(防水性「なんばん」)、瓦(不足分×1)、コーキング材(黒)、銅線(複)
築年数
30年
保証年数
2年
工事費用
16万円
 今回の工事は雪の重みによって屋根の棟瓦が崩れてしまい、崩れた部分からの雨水が浸入する雨漏りでした。1年中雨や風、紫外線にさらされている屋根は、お住まいの中で一番劣化が早い箇所となります。雪の重みによっても瓦は崩れてしまうことがあります。劣化した部分は自然に治ることはありません。放置することによって、劣化は進む一方なので、早急な処置が必要になります。
今回の工事は雪の重みによって屋根の棟瓦が崩れてしまい、崩れた部分からの雨水が浸入する雨漏りでした。1年中雨や風、紫外線にさらされている屋根は、お住まいの中で一番劣化が早い箇所となります。雪の重みによっても瓦は崩れてしまうことがあります。劣化した部分は自然に治ることはありません。放置することによって、劣化は進む一方なので、早急な処置が必要になります。一般的に棟瓦がズレているということは、屋根全体が劣化していることが多いのです。
棟瓦を固定するために使用している銅線が切れて棟が曲がってしまったり、漆喰の剥がれ、のし瓦(棟瓦の一部)がズレていたり…屋根全体が歪んでいる証拠になります。 棟部以外に劣化は見られなかったので、今回は棟瓦の葺き直し・漆喰の取り直し工事になりました。大きな地震が発生しても安心していただけるようにしっかりと施工させていただきます。
瓦屋根の場合、「瓦がズレている・漆喰が劣化してる・雨漏りがしている」といった状態のときは基本的に屋根の葺き直し、棟の積み直しが必要になります。瓦の耐久力はとても長く、一生涯使えるものもありますが、瓦の下に敷かれている野地板などの木材や防水シートは腐食していきます。その場合は腐食した箇所は交換しなければなりません。また瓦と瓦の間にはゴミや塵、ホコリなどが溜まっていきます。このゴミなどが雨水を侵入させる原因にもなるので、外観が綺麗だからと放置をせずに、プロにしっかりと内部まで見てもらう必要があります。
棟部分も同じく、漆喰が劣化していたり、銅線が切れていたりする場合は、棟瓦がズレて落下するなどの危険性を伴うので、葺き直し・棟の積み直しが必要な状態と言えます。
こちらのお宅の場合、棟瓦を撤去して現れた漆喰は、劣化が進んでいてボロボロな状態でした。瓦を固定するために敷かれる漆喰ですが、この状態になるとその役割を果たすことはできません。初めのうちは強力な保持力を持っているのですが、漆喰の寿命はおよそ10年と言われています。年月を経過する中でボロボロになり砂のようになり、この状態を放置してしまうと大きな地震が来た時など、衝撃で崩れてしまう可能性がとても高くとても危険です。また漆喰には雨水の侵入を防ぐ役割があるので、漆喰が剥がれてしまっていると棟内部の土が雨水によって崩れてしまうケースも出てくるので、漆喰を新しく交換してのし瓦を一枚一枚積み上げていく必要があるのです。
積み上げる際には耐震瓦を固定するためにコーキングと銅線を使いのし瓦を動かないようにするなど、細かな作業を丁寧に行っていかなければなりません。銅線が緩くなって瓦がズレてしまっては、瓦の落下することもあり危険です。
最近は、こういった作業をしっかりと行わずに表面を整えるだけの施工で処置をしてしまう業者がいるようです。表面上の施工だけでは、耐震の危険性はなくなりませんし、施工したことにより雨漏りを発生させてしまうこともあります。
また、20年程前の瓦屋根の場合は、瓦がビスで固定されておらずに、棟と同じ土のみで固定されているだけだった…などという事例もあるようです。
工事詳細
現地調査
「棟瓦が雪によって崩れてしまい、雨漏りがしているので修理をして欲しい」とのお問合わせを頂き、現場調査に行ってきました。
気温が低く、山に面している地方ですと、雪が多く積もって、雪害の被害がとても多くなります。
雪の重みによって瓦がズレてしまいことはよくなるのですが、実際現場に赴き屋根に登って見てみると、こちらが想像以上に被害は大きくてビックリしました。
気温が低く、山に面している地方ですと、雪が多く積もって、雪害の被害がとても多くなります。
雪の重みによって瓦がズレてしまいことはよくなるのですが、実際現場に赴き屋根に登って見てみると、こちらが想像以上に被害は大きくてビックリしました。

実際に屋根に上がってみるとよく分かりますね。
普通の状態の瓦屋根の棟部分というのは、屋根の一番高い所に一直線にまっすぐに敷かれているものなのですが、こちらの屋根は積もった雪の重さに、棟部分に敷いた瓦が耐えられなくなり、崩れてしまってしまっています。
なぜこんなにも崩れてしまったのでしょうか?
理由としては、一般的に雪というのは太陽が昇ると熱によって溶け出します。溶けた雪は屋根に勾配(傾斜)があるので、傾いた方向に重みによってゆっくりと落ちていきます。
順調に雪が溶けてくれれば問題ないのですが、この時期は天気が悪く、太陽の陽が雪が溶けるほど当たらず、気温もとても低かったのも影響して雪が溶けずにカタマリとして残ってしまったようです。
カタマリとしての状態で屋根から落ちていったために、棟部分の瓦も巻き込んで一緒に崩れてしまったのだと考えられます。
この様な状態の場合は、崩れてしまった部分のみ補修することも対処として考えられますが、漆喰(屋根を固定する部分)の劣化も十分考えられるので、棟部分の瓦と漆喰を全て取り除いて、新たに敷きなおした方がオススメの選択になります。
屋根全体を観察してみると、他の箇所の漆喰は問題なさそうです。
ですが、湿気などにより漆喰本来の瓦を固定するための粘着力が緩くなってしまい、触れると柔らかくなってしまっていたり、完全に崩れてしまっている漆喰も複数個所で確認できた場合は、劣化してしまった漆喰や破損した瓦を取り除いて、新しく漆喰を敷き瓦をのせる屋根全体の葺き替え工事を行わなければなりません。
普通の状態の瓦屋根の棟部分というのは、屋根の一番高い所に一直線にまっすぐに敷かれているものなのですが、こちらの屋根は積もった雪の重さに、棟部分に敷いた瓦が耐えられなくなり、崩れてしまってしまっています。
なぜこんなにも崩れてしまったのでしょうか?
理由としては、一般的に雪というのは太陽が昇ると熱によって溶け出します。溶けた雪は屋根に勾配(傾斜)があるので、傾いた方向に重みによってゆっくりと落ちていきます。
順調に雪が溶けてくれれば問題ないのですが、この時期は天気が悪く、太陽の陽が雪が溶けるほど当たらず、気温もとても低かったのも影響して雪が溶けずにカタマリとして残ってしまったようです。
カタマリとしての状態で屋根から落ちていったために、棟部分の瓦も巻き込んで一緒に崩れてしまったのだと考えられます。
この様な状態の場合は、崩れてしまった部分のみ補修することも対処として考えられますが、漆喰(屋根を固定する部分)の劣化も十分考えられるので、棟部分の瓦と漆喰を全て取り除いて、新たに敷きなおした方がオススメの選択になります。
屋根全体を観察してみると、他の箇所の漆喰は問題なさそうです。
ですが、湿気などにより漆喰本来の瓦を固定するための粘着力が緩くなってしまい、触れると柔らかくなってしまっていたり、完全に崩れてしまっている漆喰も複数個所で確認できた場合は、劣化してしまった漆喰や破損した瓦を取り除いて、新しく漆喰を敷き瓦をのせる屋根全体の葺き替え工事を行わなければなりません。

この状態を放置すると、屋根の状態はどんどん悪化していきます。
屋根に敷いている瓦が崩れて落下する危険性もでてきます。瓦が落下することによって、通行人や近隣の家や車などに被害がでる衝突被害も考えられますし、他の箇所に敷いてある瓦へ落下することにより被害が広がる二次被害の可能性も出てきます。
瓦の被害が広がると雨漏りの被害もますます広がることになります。
お客様へ屋根の状態と次に雪が積もった場合の被害の悪化の危険性をご説明したところ、すでに天井から雨漏りがしているらしく「早急に対処したい」とのことでした。
屋根に敷いている瓦が崩れて落下する危険性もでてきます。瓦が落下することによって、通行人や近隣の家や車などに被害がでる衝突被害も考えられますし、他の箇所に敷いてある瓦へ落下することにより被害が広がる二次被害の可能性も出てきます。
瓦の被害が広がると雨漏りの被害もますます広がることになります。
お客様へ屋根の状態と次に雪が積もった場合の被害の悪化の危険性をご説明したところ、すでに天井から雨漏りがしているらしく「早急に対処したい」とのことでした。
棟瓦と漆喰の取り直し作業


早速作業に入ります。
棟部分を横から見ると雪の重さによって瓦がズレてしまっているのが良く分かります。
ここまでズレてしまっていて雨漏りがしているということは、雨水がズレた部分から侵入している事が分かりますね。
この状態を放置しておくと、野地板などがどんどん劣化していき被害が大きくなるので早急の対処が必要です。
まずは棟瓦を固定している銅線を切る作業から始まります。
詰まれた棟瓦は崩れないように、銅製の針金で固定しているんです。
この作業は銅線と一緒に瓦を傷つけないように、銅線のみを丁寧に注意しながら切らなければなりません。
棟部分を横から見ると雪の重さによって瓦がズレてしまっているのが良く分かります。
ここまでズレてしまっていて雨漏りがしているということは、雨水がズレた部分から侵入している事が分かりますね。
この状態を放置しておくと、野地板などがどんどん劣化していき被害が大きくなるので早急の対処が必要です。
まずは棟瓦を固定している銅線を切る作業から始まります。
詰まれた棟瓦は崩れないように、銅製の針金で固定しているんです。
この作業は銅線と一緒に瓦を傷つけないように、銅線のみを丁寧に注意しながら切らなければなりません。


銅線を切り終えましたら、詰まれている瓦を取り外していく作業に入ります。
丁寧に1枚づつ外していきます。
一度に沢山の枚数の瓦を外すと、崩れてしまい瓦が落下する危険性があるのです。
時間がかかる作業ですが、棟瓦の部分は4層になっているので。2層目、3層目、4層目…と繰り返し丁寧に瓦を外していきます。
この外した瓦はまた使うので、キズや亀裂が入って割れないようにしなければなりません。
既に亀裂が入っていたり割れている瓦は、この時にまた使用しないように分別しておきます。
瓦を外していくと、中には固定するためのセメントが付いた瓦が出てきます。
この瓦も再利用するので、瓦についたセメントを丁寧に剥がしていきます。
この時に剥がしたセメントはきちんと袋にいれて作業が終わってから処分します。
丁寧に1枚づつ外していきます。
一度に沢山の枚数の瓦を外すと、崩れてしまい瓦が落下する危険性があるのです。
時間がかかる作業ですが、棟瓦の部分は4層になっているので。2層目、3層目、4層目…と繰り返し丁寧に瓦を外していきます。
この外した瓦はまた使うので、キズや亀裂が入って割れないようにしなければなりません。
既に亀裂が入っていたり割れている瓦は、この時にまた使用しないように分別しておきます。
瓦を外していくと、中には固定するためのセメントが付いた瓦が出てきます。
この瓦も再利用するので、瓦についたセメントを丁寧に剥がしていきます。
この時に剥がしたセメントはきちんと袋にいれて作業が終わってから処分します。


見てください!瓦とセメントを取り除くと、最初に瓦を定着させるために敷いていた漆喰が出現しました!
漆喰は乾燥して触るとボロボロでした。
この状態になると、瓦を接着して固定するための成分はすっかり失われているので、全く機能していないことがわかります。
このボロボロ状態の漆喰を綺麗に取り除くために、ハケなどを使って丁寧に取り除きます。
もちろんこの漆喰も袋に詰めて処分します!
漆喰を綺麗に取り除くと、次の作業への効率も良くなりますが、近隣の民家へホコリが舞ってしまい、迷惑にならない様にするためでもあります。
漆喰は乾燥して触るとボロボロでした。
この状態になると、瓦を接着して固定するための成分はすっかり失われているので、全く機能していないことがわかります。
このボロボロ状態の漆喰を綺麗に取り除くために、ハケなどを使って丁寧に取り除きます。
もちろんこの漆喰も袋に詰めて処分します!
漆喰を綺麗に取り除くと、次の作業への効率も良くなりますが、近隣の民家へホコリが舞ってしまい、迷惑にならない様にするためでもあります。
漆喰を詰め、棟瓦の施工作業


漆喰を綺麗にしたら、次の作業へ移ります。
もともと棟瓦が固定してあった周りの瓦に穴を開けていく作業です。
1枚に1か所ずつ穴をあけていくのですが、この作業をすることで瓦を固定するためにビスを打ちやすくなるのです。
あらかじめ穴を開けとくと、打ち込んだビスが途中で折れたり、しっかりと打ち込めなかったりするのを防ぐことができます。
穴が開け終わったら、土台となる漆喰を乗せていくために、周りのビスをとめて瓦を固定していきます。
瓦を固定できたら、漆喰を載せていく作業に入ります。
漆喰ははみ出しなどが無いように、しっかりと形を形成しながら乗せていきます。
この時の分量が難しく、漆喰が多くても少なくても、形が崩れたりはみ出したりしてしまうので、職人さんも集中力を使う場面になりますね!
もともと棟瓦が固定してあった周りの瓦に穴を開けていく作業です。
1枚に1か所ずつ穴をあけていくのですが、この作業をすることで瓦を固定するためにビスを打ちやすくなるのです。
あらかじめ穴を開けとくと、打ち込んだビスが途中で折れたり、しっかりと打ち込めなかったりするのを防ぐことができます。
穴が開け終わったら、土台となる漆喰を乗せていくために、周りのビスをとめて瓦を固定していきます。
瓦を固定できたら、漆喰を載せていく作業に入ります。
漆喰ははみ出しなどが無いように、しっかりと形を形成しながら乗せていきます。
この時の分量が難しく、漆喰が多くても少なくても、形が崩れたりはみ出したりしてしまうので、職人さんも集中力を使う場面になりますね!


綺麗に漆喰を乗せ終えたら、いよいよ漆喰の上に瓦を敷いていく作業に入ります。
この時の作業は鏨(たがね)という工具を使っての作業となります。
採掘現場でよく見かけるピッケルみたいなものでしょうか。
この工具を使用して、瓦を軽くたたきながら敷いていくのです。
この作業は敷いた瓦の高さを揃えるために行うので、調子に乗って強く叩きすぎたりすると、高さが合わずにデコボコになってしまうので、とても神経を使う作業になります。
この敷いた瓦は、これから上に葺いていく瓦の土台としての役目となるので、ズレが生じないように注意が必要になります。
次に、瓦と瓦の間にできた隙間を埋めるために、コーキング材を使います。
コーキング材とはゴム性の接着剤のようなものです。
そして、地震などの時に振動を吸収してくれるように、伸縮性のあるバネもこの時に取り付けます。
この作業を取り外したときと同じように、2層、3層、4層と繰り返し行うのです。
この時の作業は鏨(たがね)という工具を使っての作業となります。
採掘現場でよく見かけるピッケルみたいなものでしょうか。
この工具を使用して、瓦を軽くたたきながら敷いていくのです。
この作業は敷いた瓦の高さを揃えるために行うので、調子に乗って強く叩きすぎたりすると、高さが合わずにデコボコになってしまうので、とても神経を使う作業になります。
この敷いた瓦は、これから上に葺いていく瓦の土台としての役目となるので、ズレが生じないように注意が必要になります。
次に、瓦と瓦の間にできた隙間を埋めるために、コーキング材を使います。
コーキング材とはゴム性の接着剤のようなものです。
そして、地震などの時に振動を吸収してくれるように、伸縮性のあるバネもこの時に取り付けます。
この作業を取り外したときと同じように、2層、3層、4層と繰り返し行うのです。


こちらの写真は、元々ついていた軒先の鬼瓦です。かなりの存在感ですね!
鬼瓦は3層目の時に設置しました。
この鬼瓦も崩れないようにコーキング材と銅線を使って、しっかりと固定していきます。
コーキング材は目立たないように黒色を使用しています。
この作業をすることで、棟瓦の部分を、元の状態よりも頑丈に仕上げることができるのです。
さあ、全ての瓦を敷き終えたら、簡単には崩れていかないように、銅線をつかってしっかりと力強く瓦を固定していきます。
鬼瓦は3層目の時に設置しました。
この鬼瓦も崩れないようにコーキング材と銅線を使って、しっかりと固定していきます。
コーキング材は目立たないように黒色を使用しています。
この作業をすることで、棟瓦の部分を、元の状態よりも頑丈に仕上げることができるのです。
さあ、全ての瓦を敷き終えたら、簡単には崩れていかないように、銅線をつかってしっかりと力強く瓦を固定していきます。


瓦を固定したら、仕上げの作業へと入ります。
まずはコテを使って瓦についている漆喰を綺麗に取り除いていきます。
この作業は乾いた漆喰が他の瓦についてしまわないように行います。漆喰を取り除くと、瓦の見栄えがとても良くなるので綺麗に掃除していきましょう!
漆喰を取り除いたら、ブロアーをしようして、瓦に空気を与えていきます。
強い風を与えることによって、屋根の上からホコリや塵を綺麗に掃除することができるのです。
屋根にホコリが残っていると、雨が降った時に雨水と一緒にホコリや塵が汚れとなって流れてしまうので、外壁などを汚さないように掃除しなければなりません!
まずはコテを使って瓦についている漆喰を綺麗に取り除いていきます。
この作業は乾いた漆喰が他の瓦についてしまわないように行います。漆喰を取り除くと、瓦の見栄えがとても良くなるので綺麗に掃除していきましょう!
漆喰を取り除いたら、ブロアーをしようして、瓦に空気を与えていきます。
強い風を与えることによって、屋根の上からホコリや塵を綺麗に掃除することができるのです。
屋根にホコリが残っていると、雨が降った時に雨水と一緒にホコリや塵が汚れとなって流れてしまうので、外壁などを汚さないように掃除しなければなりません!

さあ、作業終了です!!
崩れて曲がってしまっていた棟瓦も綺麗に整っています!
これで雨漏りの心配も、棟瓦が崩れて被害が大きくなる心配もございません。
仕上がりを見て施主様からも「お願いしてよかった!これで安心して過ごせます」と喜びのお声をいただきました。
お客様の不安を解決できてよかったです。ありがとうございました!
崩れて曲がってしまっていた棟瓦も綺麗に整っています!
これで雨漏りの心配も、棟瓦が崩れて被害が大きくなる心配もございません。
仕上がりを見て施主様からも「お願いしてよかった!これで安心して過ごせます」と喜びのお声をいただきました。
お客様の不安を解決できてよかったです。ありがとうございました!
工事を振り返って
雪の重みによって棟瓦がズレてしまい、その影響で雨漏りも発生しておりました。この状態を放置しておくと、ますます雨漏りが酷くなり、棟部分の葺き直しでは対処できず、屋根全体を葺き替え工事しなければならなくなっていました。
1日という工事日数だったのですが、迅速に対応でき、とても感謝していただきました。
雨漏りだけでなく、今後地震などで瓦がズレないように、しっかりと固定して、こ雨の日も安心して過ごすことができると思います!
1日という工事日数だったのですが、迅速に対応でき、とても感謝していただきました。
雨漏りだけでなく、今後地震などで瓦がズレないように、しっかりと固定して、こ雨の日も安心して過ごすことができると思います!
雨漏り修理を依頼するにあたって期待していたこと・依頼した決め手
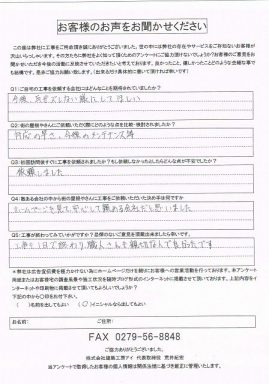
Q1:ご自宅の工事を依頼する会社にはどんなことを期待されていましたか?
今後、瓦がズレない様にしてほしい
Q2:ご依頼いただく際にどのような点を比較・検討されましたか?
対応の早さ、今後のメンテナンス等
Q3:初回訪問後すぐに工事を依頼されましたか?もし依頼しなかったとしたらどんな点が不安でしたか?
依頼しました
Q4:数ある会社の中から、弊社へ工事を発注して頂いた一番の決め手は何でしたか?
ホームページを見て、安心して頼める会社だと思いました
今後、瓦がズレない様にしてほしい
Q2:ご依頼いただく際にどのような点を比較・検討されましたか?
対応の早さ、今後のメンテナンス等
Q3:初回訪問後すぐに工事を依頼されましたか?もし依頼しなかったとしたらどんな点が不安でしたか?
依頼しました
Q4:数ある会社の中から、弊社へ工事を発注して頂いた一番の決め手は何でしたか?
ホームページを見て、安心して頼める会社だと思いました
Q5:工事が終わってみていかがですか?忌憚のないご意見を頂戴出来ましたら幸いです。
工事も1日で終わり、職人さんも親切な人で良かったです
工事も1日で終わり、職人さんも親切な人で良かったです


ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00
0120-991-887