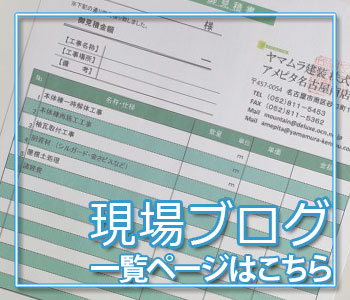名古屋市緑区にて古い屋根瓦と新しい屋根瓦の境界部分に冠丸瓦を取り付けます


以前よりも、深く被せているために雨水が越屋根の奥の方に回りにくくなっています。



こちらの記事を書いた施工店【アメピタ名古屋南店】
地元密着で屋根の工事を中心に、雨漏りの専門家として営んできました。
お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。
初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。
雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください
1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談
2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談
3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談
4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談
5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談
6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談
7.照明器具など電気工事などのご相談
8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談
9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談
お住まいの建物の屋根はもちろんのこと、内装工事も外装工事もご相談に乗ることが出来ますよ。
初動調査でもある目視による点検調査には、写真の私が責任をもってご訪問させていただきます。
雨漏りの調査以外でも、建物の営繕工事のご相談してください
1.交換時期が越えた住宅屋根の葺き替え工事や修繕・修理作業のご相談
2.建物の外壁部分の、塗り替えや外壁取り替え工事などのご相談
3.雨樋の取り替え工事などの板金工事などのご相談
4.建物内の大工さん工事である内装工事などのご相談
5.キッチンや設備など水道工事を含めたご相談
6.内壁のクロス壁紙などの貼り替えのご相談
7.照明器具など電気工事などのご相談
8.カーポートなどのエクステリア工事などのご相談
9.低層住宅と呼ばれる3階建て以下の建物の解体工事のご相談


ご希望日で無料点検を依頼

【受付時間】8:30~20:00
0120-991-887