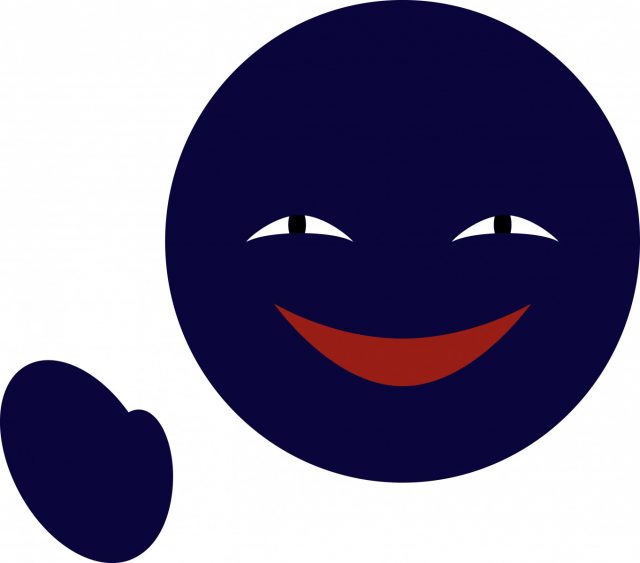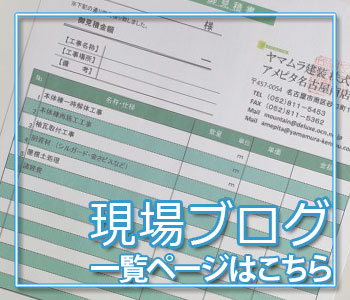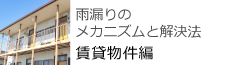2025年04月02日追記
名古屋市南区にお住まいのお客様から、悪質な訪問販売に困っているとご相談がありました。訪問業者の言葉を鵜呑みにせず、私たちにご連絡くださったのは賢明なご判断でした。お客様のお宅は築年数が経っており、屋根の漆喰が劣化しているとのことでした。現地を拝見したところ、新築以来メンテナンスが行われておらず、確かに劣化が進行していました。屋根漆喰は、住まいを風雨から守る重要な役割を果たしています。しかし、長年放置するとひび割れや剥がれが生じ、雨漏りの原因になります。お客様の安全・安心のため、劣化した漆喰を丁寧に撤去し、新しい漆喰で塗り替える工事をご提案しました。今回の塗り替えにより、屋根の耐久性が向上し、雨漏りの心配も解消されることでしょう。私たちは、お客様の住まいを末永く守るために、高品質な施工をお約束いたします。
| 施工内容 |
|
| 築年数 |
築30年ほど |
| 施工期間 |
約10日ほど |
| 工事費用 |
約70万円~ |
初動調査での注意点や契約から工事までの流れを書いています
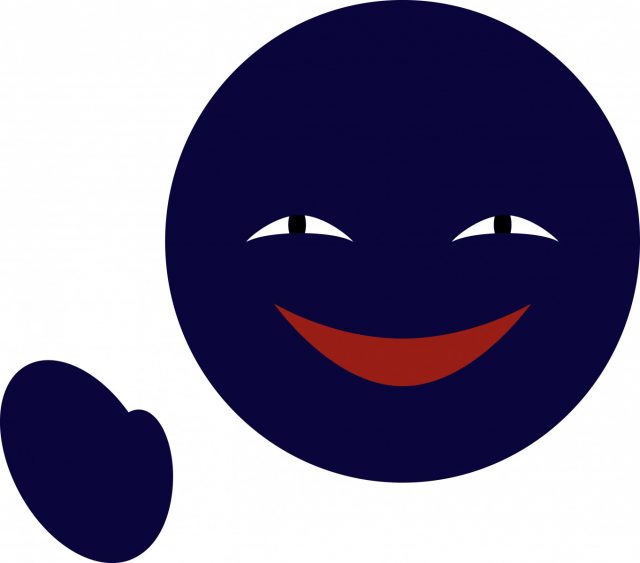 名古屋市南区にお住いのお客様より、ご相談をいただきました。築年数が経過した和風の屋根瓦の場合、よく(悪徳)訪問業者が屋根漆喰の汚れや屋根瓦の古さを見つけて、『お宅の屋根はだめですよ』と脅して仕事の契約をしていくそうです。お客様も、『信用はしていないけど心配になる』ということから、ついつい契約してしまいあとで法外な請求が来てしまうそうです。屋根漆喰も下から見ると目が遠くなるため、いつまでも綺麗に見えそうですが、屋根の上に登り近くまで寄るとかなり劣化していることがわかる時もあります。屋根漆喰は屋根瓦から雨が漏れないようにする仕事をしているので、劣化する前に塗り替えするのも必要となります。漆喰塗り替え交換の時期としては、10年~15年ほどで手を入れていくのが良いかと思います。
名古屋市南区にお住いのお客様より、ご相談をいただきました。築年数が経過した和風の屋根瓦の場合、よく(悪徳)訪問業者が屋根漆喰の汚れや屋根瓦の古さを見つけて、『お宅の屋根はだめですよ』と脅して仕事の契約をしていくそうです。お客様も、『信用はしていないけど心配になる』ということから、ついつい契約してしまいあとで法外な請求が来てしまうそうです。屋根漆喰も下から見ると目が遠くなるため、いつまでも綺麗に見えそうですが、屋根の上に登り近くまで寄るとかなり劣化していることがわかる時もあります。屋根漆喰は屋根瓦から雨が漏れないようにする仕事をしているので、劣化する前に塗り替えするのも必要となります。漆喰塗り替え交換の時期としては、10年~15年ほどで手を入れていくのが良いかと思います。
名古屋市南区に住まいのお客様より、屋根漆喰の点検のご連絡をいただきご訪問させていただきました。早速、屋根に登りすぐに目が付いた場所になります。両方に壁に挟まれて、雨水が流れやすい場所のため、壁際の熨斗瓦(のし瓦)の屋根漆喰が劣化による黒ずみが発生しています。のし瓦下の屋根漆喰に黒ずみが付く原因としては、表面を雨水が流れたときに埃カスが付く以外にも、のし瓦内部の屋根土や屋根漆喰の内側から浮き出た灰汁となります。灰汁が出るということは、のし瓦の内部にまで雨水が入っていることが考えられます。
続いて、隅棟部の屋根漆喰の状態を点検していきます。こちらも遠い位置から見ると綺麗そうに見えますが、近くに寄ると劣化が激しく所々で黒ずんでいました。それ以外にも、経年劣化による屋根漆喰に黒ずみ以外にも、穴が開きかけて破損しているところもありました。
特に鬼瓦周りの屋根漆喰は、常日頃、太陽の直射日光や風雨に当たり続けるため、経年劣化のスピードよりも劣化が激しくなりやすいです。屋根の棟部分の鬼瓦周りでも、経年劣化による屋根漆喰に穴が開き始めています。このまま放置をしていると、屋根漆喰が破損して剥がれてきます。
 鬼瓦が跨いでいる【巴瓦】の屋根漆喰も、雨風が当たりやすいため劣化が激しくなっています。
鬼瓦が跨いでいる【巴瓦】の屋根漆喰も、雨風が当たりやすいため劣化が激しくなっています。
 同じ場所の屋根漆喰でも、雨風の当たり方によっては劣化具合が違うこともあります屋根漆喰の雨漏り屋根点検を行ったあとで、お客様に『現在の状況』工事のご提案として【屋根漆喰の塗り替え作業】を提案させていただきました。後日、お見積書を作成してお客様の元へお渡しに向かいました。
同じ場所の屋根漆喰でも、雨風の当たり方によっては劣化具合が違うこともあります屋根漆喰の雨漏り屋根点検を行ったあとで、お客様に『現在の状況』工事のご提案として【屋根漆喰の塗り替え作業】を提案させていただきました。後日、お見積書を作成してお客様の元へお渡しに向かいました。
隅棟部の棟下の作業開始前の状態では、半月屋根漆喰に汚れでもある黒ずみと破損していたところが何か所ありました。この隅棟下の既存の屋根漆喰を剥がしてから、新しい屋根漆喰で塗り替えをしていきます。
同じく隅棟の棟下の半月部分になります。こちらの方も、汚れなどの黒ずみと一部半月屋根漆喰が破損していましたので、既存の半月屋根漆喰を剥がしてから新しい屋根漆喰で塗り替えをさせていただきました。
隅棟部及び大棟の棟下の屋根漆喰を塗る場所のことを【三日月漆喰】と呼ばれることもあります。
漆喰作業を専門とする左官屋さんなど一部の専門業者さんが使用する名称で、全ての業者さんが絶対に使う名称とは言いずらいですが、大棟や隅棟の棟下部分を【三日月漆喰】といわれます。
隅棟部は屋根の頂点部分の大棟部よりも、雨水が当たりやすい傾向があります。
そのため、屋根瓦に付いた埃などが雨水と一緒に屋根漆喰に当たるようになり黒ずみ汚れとなりやすいです。
雨水が当たるため、半月部分の屋根漆喰は時間とともに破損する傾向も持っています。
完全に破損しますと半月部分の屋根漆喰の下地には屋根土がむき出しになってしまい、そこから雨水が染み込み屋根裏に雨水が辿り着いてしまうこともありえます、
そのため、屋根漆喰の塗り替え機関としては『10~15年単位』での塗り替えをお勧めします。
寄棟屋根と呼ばれる屋根形状になりますが、屋根の頂点に当たる大棟部に隅棟部の棟が接続される個所のことを【三又部】と呼ばれます。この部分にも屋根漆喰を塗り、雨水が侵入しないようにしてあります。そのため常日頃、雨水に当たりやすい場所のため、他の箇所よりも劣化が激しくなってしまいます。
同様に三又部正面の屋根漆喰の状態ですが、こちらも雨水が常に当たりやすいため、劣化が激しく穴が開き窪んでいるところもあります。そのような状態のところを、すべて取り剥がして新しく屋根漆喰で塗り替えしていきました。ただし、屋根漆喰から経年劣化が原因で液だれが屋根瓦にこびり付いていました。こちらは完全に拭き取ることは出来ませんでした。
少々特殊な屋根形状ですが、棟違いと呼ばれる屋根形状の一種となります。本来は、子も胸の左右どちらかに鬼瓦など大棟部の部品があるのです。両方とも棟終いのため、屋根漆喰で大きく塗り雨水が棟に入り込まないようにしています。
一階屋根の外壁際・土居のし瓦部分になります。屋根瓦の平瓦と外壁との間に当たるところを【壁際部(土居のし部)】と呼ばれます。和風瓦(J形)の時代の名残で、外壁壁と屋根瓦の平瓦との間に取り付けられた『のし瓦』から名称が来ているかと思われます。屋根の平行になっているところを『平行壁際』と呼ばれ、こちらの屋根漆喰の部分も【三日月漆喰】とよばれることもあります。
工事完了後に、お客さまに作業中のスマホで撮影した写真を見ていただきました。
お客様も、瓦屋根が隙間なく戻っていて修復修繕されたことを確認してもらい、大変喜んでいました。初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓
『名古屋市南区にて経年劣化による汚れや剥がれた漆喰!目視にて点検調査を行いました』
お客様にご協力していただいたアンケート(お客様の声)はこちらから読めますよ↓↓↓
『名古屋市南区にて劣化していた漆喰の塗り替え工事完了後のお客様の声』

雨漏りやお住いの建物の内装工事や外装工事でお困りの際は
下記までお気軽にお問い合わせください!
受付時間 9時~17時(平日)
※定休日でも、対応していることもありますので一度ご連絡をください。
0120-806-393【フリーダイヤル】amepita@yamamura-kensou.com
※弊社は少人数での業務を行っているために、『個人のお客様』や『弊社と昔からの取引がある会社様』とのお取引を大事にしているため、新規企業様のご依頼は少しの間は受け付けをしていませんので宜しくお願いします。
トップページに戻る⇒
1.日々の現場ブログのページはこちらから移動できますよ!
2.弊社でこれまで行った施工事例はこちらから読めますよ!
3.お客様との記念写真やアンケートなどの一覧となります!